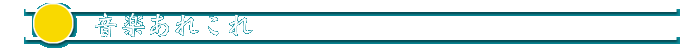
島田清純さんのエッセイ
|
コダーイ合奏団の第2ヴァイオリンを担当している島田清純さんは,本職は歯医者さんですがエッセイストとしてもかなりの腕前です。去年メサイアを練習している合間に「何か読ませて」とお願いしたところ,いくつか紹介してくれた中に音楽にまつわる傑作な文(大分以前の作だそうです)がありました。ご本人の了解を得て皆さんにご紹介します。 中村隆夫 (2003.2.22) |
|
セカンド・ヴァイオリン 島田清純
オーケストラのヴァイオリンは、二群に分かれている。ファーストとセカンド。第一ヴァイオリンと第ニヴァイオリン。誰が名付けたか知らないが、いかにも一流と二流という印象で、はなはだ宜しくない。プレイヤーたちの間では、ストバイ、セコバイなどと略して言ったりもする。ただし、実際に第ニパートを弾いている人間は、決して「セコバイ」という、まるで自らを辱めるような呼び名を使うことはない。相手の反応をちょっと気にかけながら「セカンド」と自称する。 ファーストとセカンドは、楽器が違う訳ではない。全く同じ楽器を使って、ある人はファーストを、ある人はセカンドを担当する。片方のパートは、高い音がたくさん出てきて、素敵なメロディーがふんだんに書き込まれている。もう一方は、音域も高くなく、見るからに地味で簡単そうな楽譜である。オーケストラでも室内楽でも、通常上手い方のプレイヤーが「私がファーストを弾いてもいいかしら」と言う前に、自分の方が下手だと思っているプレイヤーが「私セカンドでいいです」と言ってパートが決まる。自分が上だと思っていた方は、「あら、いいの? 悪いわね。次の曲では交替しましょうね」なんて心にもないことを言って、次の曲でも結局交替しない。自尊心を満足できた方はそのままファーストとなり、ささやかな屈辱を甘んじて受け容れた方がセカンドとして固定してしまう。何やら社会の縮図を見るようだ。 レヴェルの低いアマチェア・オーケストラでは、あまり上手くないヴァィオリン弾きを全員セカンドに閉じ込めて封印してしまうケ―スをよく見かける。彼らにはなるべく目立たず、できれば音も出さずにいてもらいたい、ということなのだ。行故かこういうオーケストラは、「セコバイ」の人数が異常に多くなる傾向がある。一度ファーストに「昇格」したプレイヤーは、もう二度とあの屈辱的なセカンドを弾かなくていいと信じている。セカンドのトップ奏者(結構弾ける人)は、いろんな意味で「くさって」、やる気を無くしている。左遷された気分なのだろう。 ヴァイオリンのセカンド・パートは、下手くそを閉じ込めておくためのステージ上の座敷牢ではないし、新参者や嫌われ者に嫌がらせをするために作られた訳でもない(もちろん退屈でウンザリするようなパート譜もあるが)。和普構成の都合上、比較的高い音を受けけ持つヴァイオリンあたりに複数のパートが必要になって作曲されているだけだ。 実際のところ、ある程度のレヴェルに達すると、合奏の面白さは、ファースト・パートよりもむしろセカンド・パートにあるのだ。何故ならば、ファースト以上に職人的な芸術性と技術の正確さが厳しく要求されるからだ。目立ち過ぎてはいけないし、かと言って消極的でもいけない。伴奏がいいとメロディーはどんどん良くなるが、伴奏が上手いという印象の演奏はいい演奏ではない。セカンド・パ―卜の出来の良さを分かるのは、指揮者とセカンド奏者と、よほど耳の肥えた聴衆だけだ。しかしそのこと自体もまた、セカンド奏者独特の、ある種屈折した喜びなのである。 私は以前、新交響楽団という社会人のオーケストラに在籍していた。このオーケストラは、ファーストとセカンドのメンバーをどんどん入れ替えることでレベルアップを図っていた。丁度その頃私はセカンドを担当していた。音楽監督芥川也寸志先生の指揮で、ベルリオーズの「ローマの謝肉祭」という曲を練習していたときの話。セカンドの最弱音でのリズムの刻みから始まり、それにだんだん楽器が加わって段階的に最強音まで達するという部分があった。これが大変難しい。まず最初は、ほとんど聴こえないくらいまでに音量を下げるための脱力と、リズムの正確さや緊張感を維持するための速くて細かい運動が両立しにくい。全体の音が大きくなると、セカンドのリズム形は管楽器のメロディーに埋もれてしまって、ほとんど音響的な意味を成さない。困った我々は、試行錯誤の末、ある形に到達した。最初の弱音では、全員楽器を自分の体で隠してしまうほどに体を小さく折りたたむ。音量の増加と共に(実際はそんなに音量は出ない)徐々に体を開き、弓使いを大きくする。最後は弓をぶんぶん振り回し、楽器本体は頭の上で旋回する。音量以上に得られる演奏効果は、メロディーを受け持つメンバーをより積極的にさせ、素晴らしく開放的な音が出てきた。 芥川先生、思わず微笑んで一言。「セカンド、いいね」 私たちセカンドのメンバーはその晩乾杯した。鬱憤晴らしではなく、本当に嬉しくて。 世の中には、何でも一番になりたがる人もいる。けれど人生、脇役の楽しみというものもある。しっかり足が地に着いた脇役の方が、音楽も生き方も私の性に合っている気がする。三十代にしてはちょっと地味かなあ。 |
バックナンバ-ー
Vol.01ヘンデル「メサイア」について Vol.02「メサイア」作曲上の秘密
ウィーンからのメール メサイア演奏上の諸問題
札幌コダーイ合唱団 All rights reserved
sapkodaly@cool.ne.jp